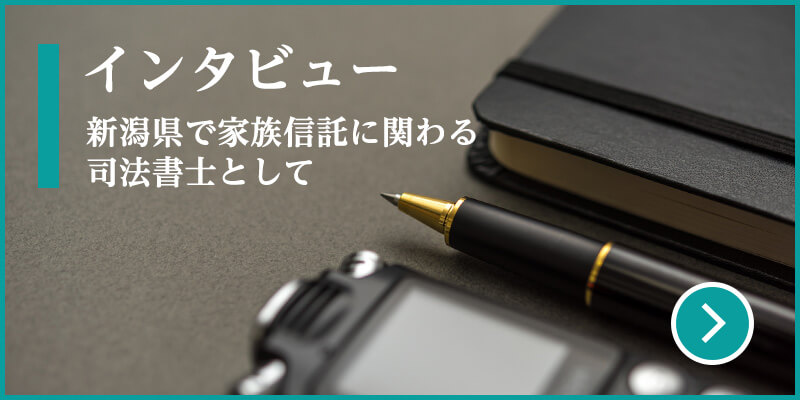近頃、認知症になると口座が凍結してしまうという話をよく耳にします。
私の母は新潟で一人暮らしをしていますが、ほとんど貯金もなく年金をやりくりして生活しています。
まだまだ元気ですが、認知症になったとき年金を受け取っている口座が凍結されてしまったら、いろいろな支払いが滞ってしまいますし、
息子である私が負担することにもなると思います。もちろんいざとなれば私の負担で助ける気持ちはありますが、出来る限り年金で何とかしてもらいたいと思います。
年金の受け取り口座が凍結してしまうかもしれないことに対して、何か備えをすることは出来るのでしょうか?

ご相談ありがとうございます。
元気なうちに家族信託契約を結び、その中で 自動送金サービスを利用して、年金口座から信託口座へ定期的に資金を移す仕組み を作っておくことができます。以下解説いたします。
認知症による年金口座凍結のリスク
多くの高齢者は年金口座を生活の基盤にしています。
しかし、認知症などで判断能力を失うと、銀行は「本人の意思確認ができない」と判断し、口座からのお金の引き出しを制限する(凍結状態) ことがあります。
この場合、まだ生存しているのに、生活費や医療費の支払いに支障が出てしまう可能性があります。
このケースでは、お母さまを委託者兼受益者、ご相談者様を受託者として、家族信託を組むことで、このリスクに備えることができます。
家族信託と自動送金サービスの仕組み
年金口座から信託口座へ自動移動
-
年金はまず本人の年金口座に振り込まれる(年金受給は一身専属権ですので、本人口座にしか振込されません。)
-
年金受取口座から信託口座へ自動送金サービスを設定しておけば、毎月一定額が信託口座へ移動する
-
受託者(信託を任された家族)が信託口座から生活費や施設費を支払う
この流れを作っておくことで、認知症による口座凍結リスクに備えることができます。
自動送金サービスの落とし穴
利用期限がある場合がある
一部の金融機関では、自動送金サービスに 「数年間で契約終了」 という期限を設けています。
契約が切れてしまうと更新手続きが必要ですが、認知症になった本人は手続きできません。
その結果、送金が止まり、信託口座に資金が入らなくなるリスクがあります。
銀行ごとの対応の違い
銀行によって、自動送金や信託口座の取り扱いに差があります。
「この銀行ではできるけれど、別の銀行ではできない」といったケースもあるため、事前確認が必須です。
トラブルを防ぐためのポイント
-
銀行に確認する:自動送金の有効期限や条件を必ず聞いておく
-
受託者が定期的にチェックする:送金状況や期限切れを年に1回は確認
-
代替策を用意する:自動送金が止まった場合に備えて、代替の方法を準備しておく
まとめ:自動送金は便利だが「期限」に注意が必要です
家族信託と自動送金サービスを組み合わせれば、認知症による口座凍結に備えて生活費を安定的に確保できます。
しかし、
-
年金は信託口座に直接振り込めない
-
自動送金に期限がある場合がある
-
銀行によって対応が異なる
といった落とし穴があります。
「仕組みを作って終わり」ではなく、継続的な確認とメンテナンス を行うことが、安心した老後の生活につながります。