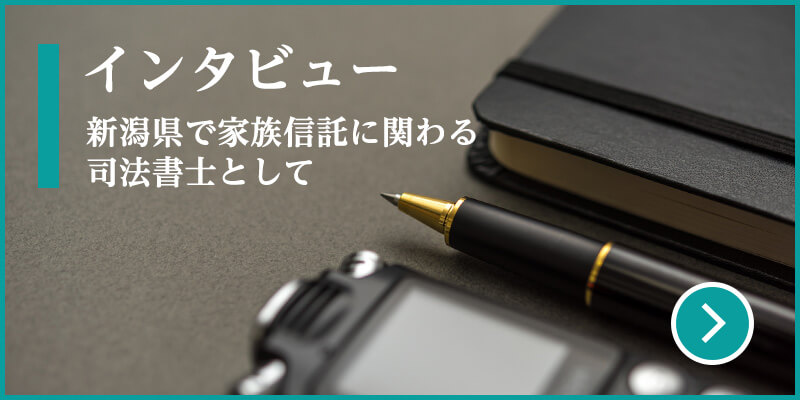相談者:新潟市80代女性
◆ 受益者連続型信託とは?
受益者連続型信託とは、ある受益者が死亡した後に、次の受益者が自動的に利益を受け継ぐ仕組みです。
たとえば、以下のような流れになります。
- 初代受益者:あなた(相談者様)
- 次代受益者:長男
- 三代目以降:お孫さん
この仕組みにより、遺言や相続手続きなしに財産の承継先を明確に定められるため、相続トラブルの防止にも役立ちます。
◆ よくある設計案
相談者様がお聞きになったのは、恐らく次のような形です:
| 役割 | 当初 | あなたの死亡後 |
| 受託者 | 長男 | 長男(継続) |
| 受益者 | ご相談者様 | 長男(次代) |
一見するとシンプルで合理的な構成に見えますが、ここに落とし穴があります。
◆ 信託終了のリスク:「1年ルール」とは?
信託法第163条では、次のように定められています。
「受託者が単独で受益者となったときは、その状態が1年間継続した時点で信託が終了する」
つまり、受託者と受益者が同一人物になると、信託が1年後に終了してしまうのです。
🔍 ご相談者のケースで考えると:
あなたが亡くなった後、
- 長男が受託者であり、かつ
- 受益者として信託財産からの利益を受け取るようになる
→ この時点で、受託者=受益者の一致状態となり、「1年ルール」のカウントが始まります。
そのまま1年経過すると、信託は自動的に終了してしまうのです。
これでは、本来の目的である「孫への財産承継」まで到達できないおそれがあります。
◆ 回避策と設計の工夫
このような信託終了リスクを避けるには、以下のような対応が考えられます。
✅ 1. 受益者を複数にする
長男以外にも、例えば次男や孫を共同受益者にすることで、「長男=唯一の受益者」状態を避けることができます。
✅ 2. 長男を受託者から外す(又は途中で交代させる)
長男を「受益者」に専念させ、別の親族を次の受託者に設定する方法。
→ これが最も確実で、「1年ルール」適用の心配がなくなります。
✅ 3. 受託者を法人とする
法人は人とは別人格なので、長男が受益者となっても信託終了にはなりません。
◆ 応用編:「受託者が複数で受益者がその一人」の場合は?
たとえば、
- 受託者:長男と次男(共同受託者)
- 受益者:長男のみ
この場合、**「受託者=長男+α」「受益者=長男」**なので、
「完全に一致していないからセーフでは?」と考えられがちですが…
⚠ 実務では要注意
このような一部一致のケースでも、「実質的に同一」と評価される可能性があるため、油断はできません。
判例や学説の蓄積が少ない部分であり、安全策を取るべきです。
◆ まとめ
- 受益者連続型信託は、資産承継に有効な手段
- しかし、「受託者と受益者が同一」になると1年で信託が終了するリスクがある
- ご相談のケースでは、長男が受託者・受益者を兼ねる設計は要注意
- 安全に継続させるには、受益者を複数にする、受託者と受益者を分離するなどの工夫が必要
◆ 最後に
信託の設計は自由度が高い反面、一つの条件を見落とすと想定外のリスクが生じます。
特に「1年ルール」は、表向きの構造では気づきにくいため、設計段階での綿密な検討が不可欠です。
信頼できる専門家と連携して、ご希望どおりに土地が代々受け継がれるような設計を実現しましょう。